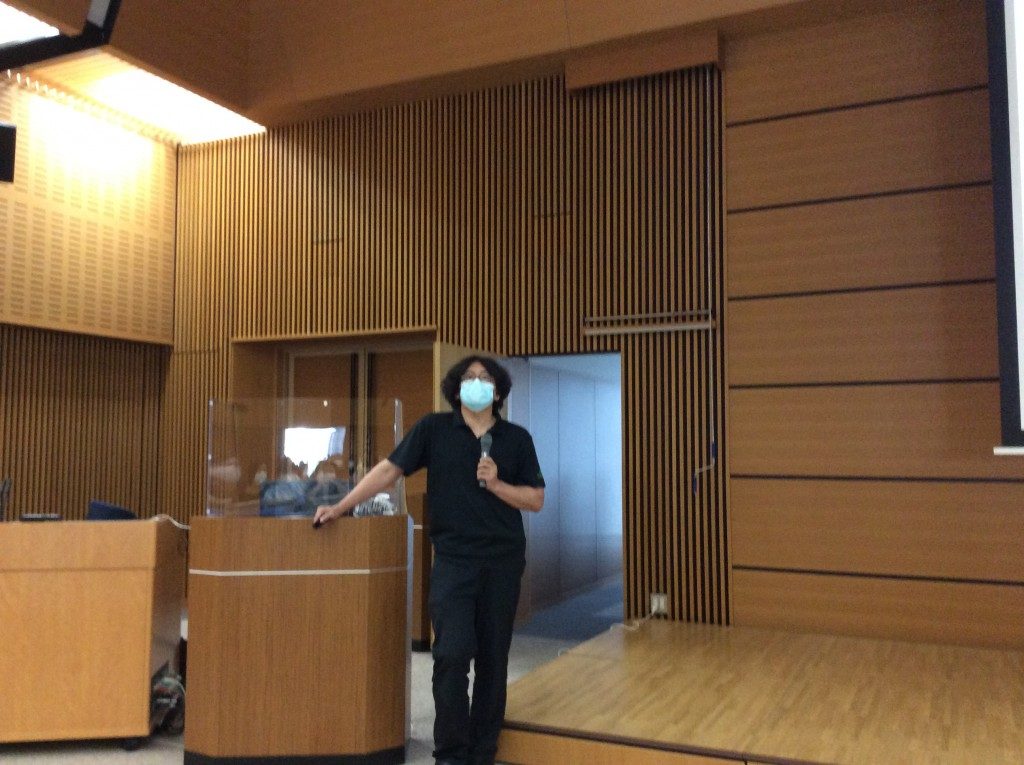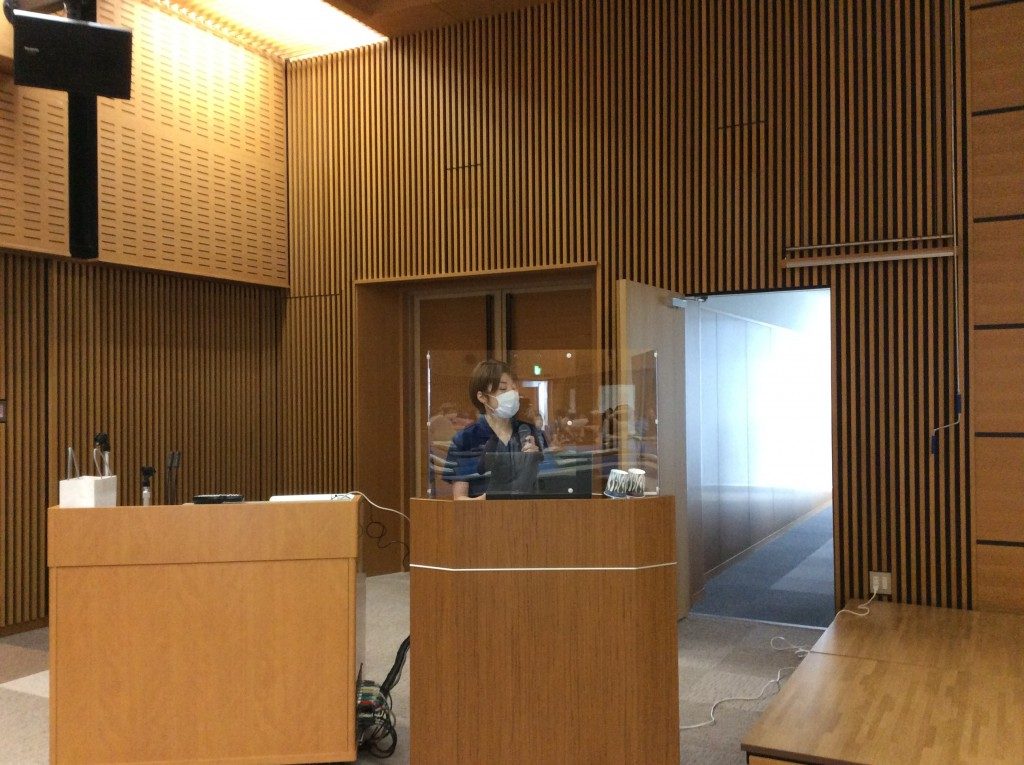ポピーインタビューVol.7 大沼智之歯科医師(大沼歯科医院 院長)
今回は山形市内の在宅歯科診療にご尽力くださっている大沼智之先生にお話を伺いました。

大沼智之先生1-2
〇先生が歯科医師を志すきっかけとなったエピソードや動機などを教えてください。
祖母が歯科医を始めて、両親、弟も歯科医です。幼いころに見ていた歯科医の父は、診療が終わった後も夜遅くまで技工の仕事をしていました。書物を読んで勉強する姿もたびたび見ていましたし、勉強嫌いな自分は、勉強ばかりしなくてはならないのなら歯科医にはなりたくないと思っていました。自分としては数字が好きでしたのでそういう方面に進みたいと思っていたのですが、いよいよ進路を決める時には長男だから…と自分なりの覚悟を決めたように思います。
〇学生時代はどのように過ごしましたか?
山形から新潟の海沿いにある大学に進学したのですが、海沿いをバイクでツーリングするのがとても気持ちよくて楽しかったです。学びについても興味を引くものに出会い、面白いと思える分野に進むことができました。卒業後も大学に残り歯科補綴(ほてつ)学(入れ歯や差し歯、ブリッジ、顎関節症、かみ合わせなどの分野)を専門に16年学びました。学ぶたびに知識が増え、できることが増えていく、そのことに楽しさを感じていました。
〇先生は在宅歯科診療もされていますが、在宅歯科診療を始められたのはなぜですか。
山形市歯科医師会では全国でも早い時期に在宅歯科診療を始めています。そこには私の父も関わっていましたので、あたりまえに目の前に在宅歯科診療がありました。大学病院の診療でも訪問歯科診療チームに入っていたので訪問する機会もありました。在宅歯科診療はわたしにとって特別というイメージはなく、とても自然に、身近にあったと思います。訪問歯科診療は診療以外の時間を利用して患者さんのお宅を訪問することが多いのですが、歯科衛生士の妻も同行してくれています。訪問歯科診療に理解してくれている妻がいるので環境に恵まれていたというように思います。
〇先日、国民皆歯科健診の実現に向けて国が動き始めました。近年では特に口腔内の健康状態と様々な疾患の関連についての話題を聞くことが多くなったように感じます。
パンフレットやリーフレット等は以前より良く見かけると思います。例えば、山形市では母子健康手帳にも妊娠中の口腔衛生と低体重児出産の関連について掲載するようになりました。さらに、2~3年前から始まった妊産婦歯科健診を通じて安全な出産や乳幼児の健やかな発育と妊産婦の口腔衛生との関わりについて、それに加え40歳50歳60歳70歳75歳の方への歯周病検診では、歯周病と全身疾患との関連も説明しており、関心を持ってもらえるようになったと思います。また2年前の保険改正で「口腔機能低下症」が病名収載され、高齢者には口腔機能に着目したフレイル予防増進など、まだまだ周知の必要性はありますが、各ライフステージに応じた対応をしていくことが大切だと感じています。
〇口腔内を健康に保つことはフレイル予防にも関連し、健康寿命を伸ばすことにもつながりますが、なぜでしょうか。
フレイル予防や健康寿命の延伸には、適切な栄養摂取は重要です。口腔衛生の低下により歯周病やう蝕で多くの自分の歯を喪失したにもかかわらず義歯等で補わず放置したり、多くの自分の歯があっても、あまり嚙まなくてもよい食事ばかりしていて嚙む力が低下してれば十分な咀嚼ができません。それでは食の多様性が低下し、十分な栄養を取ることができなくなってしまいます。以前、デイサービスに通う利用者600名を対象に栄養状態と口腔内の状況を調査しました。調査の結果、よく噛める方は栄養状態が良く、よく噛めない方は栄養状態が良くない傾向にあることがわかりました。山形の方は困っていても我慢される方が多い印象があります。特に口の中は身体よりも後回しになってしまう傾向にあり、いよいよ何とかしないとどうしようもない状況になるまで我慢される方もいます。我慢せず、早めの受診をしていただきたいと思っています。
〇では、口腔内を健康に保つための秘訣を教えてください。
やはり、かかりつけ医を持つのと同じようにかかりつけ歯科医を持っていただくことだと思います。定期的にチェックしメンテナンスを行うこと、予防ですね。そして歯も身体と同じく早期発見・早期治療が大切です。困っていたら気軽に相談していただきたいと思います。
〇在宅の患者様の口腔内を診ていて感じていることがありましたら教えてください。
以前に比べると口の中への関心が高まっていると感じます。医療や介護の現場では口腔ケアと誤嚥性肺炎の関連が言われるようになり、介護現場でも注意してくださるので訪問診療の依頼も多くなりました。一方、厚生労働省の資料では要介護者の75%の方には歯科治療が必要ですが、実際に受療につながっている方は27%にとどまっているのが現状です。お口の中の問題を我慢せず相談していただき、より多くの方を受療につなげていただきたいです。歯科受診の必要性を判断するために活用できるツールとして山形市歯科医師会で作成した「お口の問題チェックリスト」があります。患者さんの症状やお困りのことから歯科治療の必要性について気づくことができるチェックリストになっています。ぜひ皆さんに活用していただきたいです。
山形は在宅歯科診療に関わる歯科医師の割合が全国でもベスト5に入るほど多い県です。こんなに豊富な医療資源があるのですからぜひ地域の方々に在宅歯科診療を活用していただき、もっとこの地域に浸透していけたらと思っています。
〇地域の医療福祉関係者との連携で感じていることや先生自身が心掛けていることなどがありましたら教えてください。
顔の見える関係とよく言いますが、できるだけ直接会って話すようにしています。職種によって同じ言葉でもニュアンスが違うことがあるので、直接話すことで言葉をどのように受け取っているか理解できると感じています。
MCSも在宅歯科診療では大変役に立つと思います。患者さんのお口の中の情報、歯肉の腫れや出血などの症状を言葉で表現するのは難しいですが、MCSでは撮った写真を送ることができます。お口の中の写真をいただくことでその患者さんに必要な処置、必要な器具を予測することができ、最初の訪問から治療することができるので助かります。相手の連絡先を知らなくてもMCSだとつながることができるのもいいですね。
〇最後に、先生の休日の過ごし方(趣味など)を教えてください
妻がドラマや映画を撮っていてくれるので、お酒を飲みながら二人で見るのが楽しみです。
それと、スキューバダイビングです。実は幼いころにジョーズという映画を観たのですが、衝撃と恐怖心があったので「海に潜るなんて絶対にやらない!!」と思っていましたが、妻と旅行に行ったときに妻に誘われて初めて潜りました。目の前に別世界が広がっていて「こんな世界があるのか!!」と感動し、夢中になってしまいました。
〇大沼先生、ありがとうございました。
大沼先生は「甘いものも食べていいし、もちろん前提にだらだら食べをしないこと」や「歯周病予防のためには、1日何回歯磨きしたかではなく1回しっかり磨けばいい。意外かもしれないけど意外な方が記憶に残るでしょ?」とお話されていらっしゃいました。幼いころに見た歯医者さんの待合室の「お砂糖は敵!甘いものは虫歯の原因!ミュータンス菌が歯を溶かす!!」という絵本やポスターのイメージが強かったので、まさか歯科の先生から甘いものも食べていいと言われたことに新鮮な驚きを感じている自分がいました。そして、先生のお話の中には山形の方々の特徴や暮らし、生活、楽しみ、などの言葉もたびたび登場し、お会いした数時間で歯科診療や口腔ケアに対して、豊かな食、豊かな暮らし、食べることを楽しむ、等のイメージを持つことができました。先生が、ご自分の置かれた環境が恵まれていたと度々話され、穏やかに優しくお話しくださる姿、ひとつひとつ言葉を聞いていただいた上で疑問にも真摯に答えてくださる姿から地域の専門職からの信頼が厚い理由を感じました。今後のご活躍を楽しみに思います。(K.U)
過去のポピーインタビューはこちらからご覧いただけます。 Vol.1 根本元医師(在宅医療・介護連携室ポピー室長・根本クリニック院長) Vol.2 峯田幸悦氏(山形県老人福祉施設協議会・ながまち荘施設長 Vol.3 大島扶美医師(医療法人社団・社会福祉法人悠愛会理事長) Vol.4 山川淳司氏(元小規模特別養護老人ホーム大曽根施設長/現盲特別養護老人ホーム和合荘) Vol.5 髙橋邦之医師(髙橋胃腸科内科医院 古舘診療所・飯塚診療所所長) VOl.6 神谷浩平医師( MY wells 地域ケア工房代表 )
ポピー研修会「在宅療養について学ぶPART1~在宅医療サービスとチーム連携~」を開催いたしました
令和4年7月20日(木)13:30~ 山形市医師会4階大会議室にて標記研修会を開催いたしました。コロナ禍で集合型の研修会は開催が難しく、なかなか開催できずにおりましたが、感染状況の動向を注視し、ようやく開催することができました。
92名の多職種の方々にご参加いただきました。(4階大会議室にこんなにお集まりいただいたのは2年半ぶりのことだと思います。)
訪問診療についてのお話を、訪問診療クリニックやまがた 院長 奥山慎一郎医師、医療ソーシャルワーカー 五十嵐絵美氏よりいただきました。
訪問看護についてのお話を、訪問看護ステーションやまがた 山川一枝氏、訪問看護ステーションいぶき 管理者 渡邊健氏 よりいただきました。

IMG_0202-1 
ライフサポートセンターめだかの山口眞紀子氏からは、ケアマネージャーのお立場からみた在宅におけるチーム連携についてお話をいただきました。
参加者の皆様のアンケートからは94%の方々に「活用できる」「大体活用できる」と回答をいただき、多くの感想をいただきました。
この研修会は「在宅療養について学ぶPART2~医療依存度の高い方の退院支援と在宅看取り~」オンライン研修会へと続きます。皆様のご参加をお待ちしております。
ポピーインタビュー Vol.6 神谷浩平医師(MY wells 地域ケア工房代表)
今回は、緩和ケアの分野で活躍されている神谷浩平先生にお話しを伺いました。
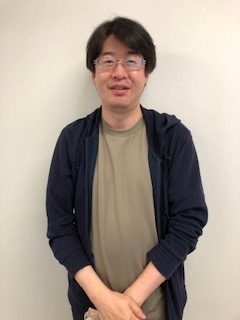


※神谷先生の活動:2001年、山形大学医学部卒業。同附属病院麻酔科、山形県立中央病院麻酔科を経て、筑波メディカルセンター病院緩和医療科へ。 2010年に山形県立中央病院緩和ケア病棟医師として入職、翌年、同院緩和医療科医長に就任。2020年に退職し、一般社団法人MY wells 地域ケア工房を設立し、コンサルタントとして独立。日本緩和医療学会・緩和医療専門医。
ポピー:以下ポ)
神谷先生の子供時代について教えてください。幼いころ、どのような少年でしたか?
本を読むことが好きで、人前で話すのが苦手な少年でした。成績も優秀でない・・・(笑)。でも、高校生の時に合唱部に入り歌ったり、指揮をしたり、大学生の時には合唱部を作りオペラや舞台芸術の場で歌ったりしていたので、自然と人前に出ることに抵抗がなくなっていきました。
ポ) 医師を志すきっかけとなったエピソードや動機などはありますか?
医師を志すきっかけは、中学生の頃、「病院で死ぬということ」という本を読んでのことです。死を迎えるという自分の力ではどうにもならない人生の大きな局面にいる病気の人の、苦しい思いや辛い思いを知り、それを支えたいと思い、医学の分野に興味を持ち始めました。
ポ) なぜ、緩和ケアを専門に深められたのですか?
緩和ケアは新しい分野だったので関心を持った、ということもありますが、麻酔科で診療していた頃、患者さんやご家族は、身体的な痛みだけでなく手術への不安、誤解等の大きな心理的な負担を抱えており、安心安全な入院生活を送るためには苦痛の緩和とともにコミュニケーションが重要である、ということに気付きました。そして、単に痛みを取るだけでなく、患者さんやご家族の不安や病状、家での生活が今後どのようになるか等について、全人的に向き合う医療が大切であると考えるようになり、次第に緩和ケアへの関心が強くなっていきました。他の先生からは、「患者の人生を見るような歳ではない、まだ早いよ」と、よく助言いただきました(笑)。確かに長い臨床経験を積まれてから緩和ケアに進まれる医師も見てきましたが、経験や年齢に関わらず、専門領域として緩和ケアを学びながら患者さんに関わっていくことは、意味のあることだと思っています。
ポ) 患者様との関わりのなかから特に印象に残っている場面などがあったら、差し支えない範囲で教えていただけますか?
緩和ケアのコンサルタントの仕事をしていると、テレビドラマが陳腐に見える位、患者さんとの関わりは色濃く、全て印象に残っています。余命1、2週間で、骨の痛みが強くあお向けにもできない病状の20代の男性患者さんの話ですが、「痛みが取れたら何をしたいですか?」と質問したところ、「結婚を約束した女性と家族でディズニーランドに行きたい。」と話されたので、「だったら、ここからが私たちの腕の見せ所ですね」と伝えました。後でその患者さんは、「その言葉が一番うれしかった」と話されていました。緩和ケアとして自分がやっていることは、その人にとって良いのかどうか自問自答したり、時に、無力さを感じる時もあるわけですが、患者さんに対し医療者が、「自分たちも頑張るから一緒にがんばりましょう」と、最後まであきらめない姿勢で関わることはとても大切な事だと感じています。明日、亡くなるぐらいの人が、もう一回海を見てみたいと話されたとすると、「なぜそう思われるか、教えていただけませんか」や、「そうなると、本当にいいですね、そうなるためにどうすれば良いでしょうね」と、患者さんがなぜそのような思いでいるのか、何を言って欲しいかを感じられると良いと思います。
ポ) 緩和ケアを地域の医療機関に広く普及するためのコンサルタント活動をされて2年、現在の活動内容や、感じていらっしゃることを教えてください。
今、頑張っているのは各病院の緩和ケア支援体制の強化です。スタッフへのアドバイスが中心ですが、直接、診察することもあります。緩和ケアは、医師、看護師等、チームとして取り組むことが非常に大切であり、その考えが今後普及していくことが必要です。そして、この2年間で見えてきたことは、症状をスクリーニングし、アセスメントするシステムの必要性です。具体的には痛みの程度、お困りの強さ、どのように困っているのか、緊急性はどうか、誰が、いつ、どのように問いかけるか等、ルール化したアセスメントが医療チームで可能になることです。患者さんの苦痛については、包括的な視点から情報を医師、看護師等と共有し、チームで客観的に評価し、ケアや生活の質が上がったのかどうかの評価に繋げていきます。生活の質を保つ視点については、痛みをとるだけが緩和ケアではない、重要な要素と位置付けています。
ポ) 先生の目指す緩和ケアの在り人や、地域の多職種に期待することはありますか?
地域の多職種に期待することは、患者さんやご家族、スタッフ間でのより質の高いコミュニケーションです。患者さんの生活の質がイメージできるような関わり持つことは大切ですが、そこを多職種に繋ぐのは多くは看護師の役割です。そのためには、「患者さんが自分の想いを話してくれない」、と患者任せにするのではなく、コミュニケーションのトレーニングをして、患者さんの言葉を待ち、自然に引き出せていけると良いと思います。話し合いの質を上げる技術のトレーニングについては、アメリカのハーバード大学で考案された、「重い病気を持つ患者との話し合いの手引きケアプログラム(SICP)」があります。ACPと言ってもそれができないと、患者さんの大切にしていることや、価値観、気がかりなどに焦点を当てた話し合いのプロセスにはなり得ません。こうしたマニュアルを活用しながらチームで取り組み、医療的な面でのゴールだけでなく、患者さん自身が人生の中で大事にしてきたこともゴールとして医療が役立っていけるよう、取り組んでいきたいと考えています。
ポ) 最後に、先生の趣味や休日の過ごしかたなど教えてください。
「趣味は、音楽を聴くことや合唱でしたが、最近はできていません。休日は少しでも体を休めつつ、おいしいコーヒーを入れて飲むことや、本を読んだりするなど、基本的にインドアな過ごし方をしています(笑)。仕事を兼ねたドライブが好きなので助かっています。」
ポ) 先生自身が召し上がりたい最後の晩餐を教えてください。
「その時になってみないとわかりませんが、普段のご飯がおいしいと感じられて、食後に美味しいケーキと珈琲をいただければ嬉しいです。または、きっと口が渇いているので、アイスクリームや果物など、冷たいものでさっぱりして終わりたいかな、と。」
神谷先生のインタビューを終えて
先生の話を伺って、緩和ケアというのは、単に患者さんの痛みを緩和するだけでなく、「全人的な視点で心に寄り添い癒し、生活の質を高め、幸せを全うできるよう支えていく医療である」ということを理解することができました。柔らかに話される先生が、仕事の話になると真剣な眼差しで熱く話される姿が、印象的でした。
神谷先生、ありがとうございました。
過去のポピーインタビューはこちらからご覧いただけます。
Vol.1 根本元医師(在宅医療・介護連携室ポピー室長・根本クリニック院長)
Vol.2 峯田幸悦氏(山形県老人福祉施設協議会・ながまち荘施設長)
Vol.3 大島扶美医師(医療法人社団・社会福祉法人悠愛会理事長)
Vol.4 山川淳司氏(元小規模特別養護老人ホーム大曽根施設長/現盲特別養護老人ホーム和合荘)
Vol.5 髙橋邦之医師(髙橋胃腸科内科医院 古舘診療所・飯塚診療所所長)
<報告> ポピーのACP(人生会議)普及啓発活動
ポピーでは、ACP=アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)を、多職種連携のキーワードと位置づけ、地域包括支援センターの協力のもと、 専門職向け、住民向けの講座の講師を担当してまいりました。
今年度は11月末までに、ケアマネジャーを中心とする専門職向け4カ所84名、住民向け3カ所233名、住民向け講座の録画配信22事業所64名↑の参加を得ました。
専門職からは「日頃のコミュニケーションを図ることで、ACPにつなげられる」「アドバンスケアプラニングのingが進行形である意味が分かり、状況に合わせて変化してよい。決める過程の多職種連携が重要だとわかった」などの感想がありました。
住民からは「人生会議は忘れられない言葉です」「人生会議の話を聴いて元気が出た」「妻と話してみたい」「夫と話してみたい」などの前向きな感想がありました。